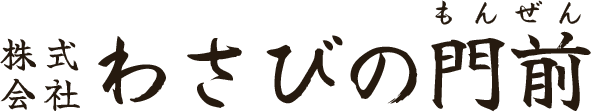クラス
txwh :白字強制
img20 ~ img60 :it01 ti01の画像幅を変更
noStep :fb_flow01のステップを削除
sheet :シート、内余白が付きデフォルト背景色var(--bc)
お仕事概要
有東木でのわさび田は「畳」と呼ばれる独特な田で作られます。(工事費坪3~5万)
「畳」は大きな石を1番下に敷き徐々に大きさを小さくして,地面の表面20cmくらいの砂状の作土を敷いたものです。こうする事によって、水が表面7~8割、直下に2~3割流れわさびの根の先まで水がいきわたり、わさびが大きくなるのです。
上記のように特殊な、わさび田ですので、それなりの日頃の手入れが必要となります。
普段は20センチほどの厚みの作土の部分のみを耕運したり泥流しをします。
それでは、わさび仕事を順を追って紹介します。
「畳」は大きな石を1番下に敷き徐々に大きさを小さくして,地面の表面20cmくらいの砂状の作土を敷いたものです。こうする事によって、水が表面7~8割、直下に2~3割流れわさびの根の先まで水がいきわたり、わさびが大きくなるのです。
上記のように特殊な、わさび田ですので、それなりの日頃の手入れが必要となります。
普段は20センチほどの厚みの作土の部分のみを耕運したり泥流しをします。
それでは、わさび仕事を順を追って紹介します。

収穫後のわさび田
1年半 御苦労さま!さあ また大きく,きれいなわさびが揃って出来るように整備します。白くみえる波板は下の段に落ちる水が飛び散らない様にするためのものです。

ごみとり
わさびの葉っぱや木の葉、また地面に切れて残っている わさびの毛をとります。
ていねいにとらないと 次回植え付けるわさびが腐りやすくなるので、おろそかに出来ません。
道具はわさびの毛取りは手で、それ以外は熊手を使います。
ていねいにとらないと 次回植え付けるわさびが腐りやすくなるので、おろそかに出来ません。
道具はわさびの毛取りは手で、それ以外は熊手を使います。
どろ流し

わさび田にはわき水が流れているのですが、回りの山から1年の間にはどろが入ったりしているので、2馬力ほどのポンプで泥を流します。
長年の勘を要する仕事です。
長年の勘を要する仕事です。

流した泥が他のわさび田に入らない様にする、いろんな方法がありますが、家では泥流し用の施設が無いところでは写真のように、水が落ちる際に幅25センチくらいの板の10センチほどを埋め込み、下のわさび田に、泥水がいかないようにします。たまった泥水は、黒パイプに集め川に流しています。

これが泥流し用ポンプです

水切り
作土を耕運機で攪拌するとき、 作土が良くまざるように水切り(水を流さないように)します。
わさび田には 暗渠(あんきょ)と言う穴がわさび田の上部にあり、そこに水を集めて落とします。
暗渠に落ちた水はすぐ下の段のわさび田に出てきます。
わさび田には 暗渠(あんきょ)と言う穴がわさび田の上部にあり、そこに水を集めて落とします。
暗渠に落ちた水はすぐ下の段のわさび田に出てきます。

暗渠(あんきょ)
水切り(水を流さない)の時や水が台風などで多くなったりした時水量の調節をするために作ってある、わさび田の地中に作ってある水路。

わさび田くわ
これが特注わさび田くわです。じゃりの中を軽く耕える様に作ってあります。一番大事な道具で、これさえあれば作業のほとんどができるので、とても大切にしています。
全長80センチ 重さ1.3キロ
全長80センチ 重さ1.3キロ

耕運(こううん)
表面から20センチの作土の部分だけが よくまざるように耕運機をかけます。 そのあと最低3日ほど作土を良く乾かします。よく乾かす事により水生害虫を殺虫剤を使うことなく やっつける事ができます。また作土の状態がよくなります。

ホンダこまめちゃん
最初の頃は軽くて力もあっていい耕運機だなーと思っていたのですが(確かに今でも4サイクルの耕運機としてはとても軽い方なのです)
しかしそれでも重い!(30kg)
わさび田は山の斜面にあり足場が悪く、また、わさび田の面積も小さいので移動する事が多いので大変です。
しかしそれでも重い!(30kg)
わさび田は山の斜面にあり足場が悪く、また、わさび田の面積も小さいので移動する事が多いので大変です。

土ふみ作業
わさび田を散歩している写真ではありません。耕運した状態でそのまま水を流すと作土が柔らかすぎるため植え付けた苗が倒れてしまいます。
そこで土を踏んで少し固めておきます。
そこで土を踏んで少し固めておきます。

ならし作業
わさび田へ均一に水が流れるように、ゴルフ場で見るアルミのならし棒でわさび田を平らにします。
このときわさび田の斜度は2%(水の流れてくるほうに1m行って2センチ上がる斜度)程に調整します。この斜度位が、有東木でのわさび栽培には適しているようです。
ちなみにわさび田を流れる水の厚みは、1センチから2センチくらいになります。
このときわさび田の斜度は2%(水の流れてくるほうに1m行って2センチ上がる斜度)程に調整します。この斜度位が、有東木でのわさび栽培には適しているようです。
ちなみにわさび田を流れる水の厚みは、1センチから2センチくらいになります。

植え付け作業
さあ!わさびを植え付けます。 こればっかりは機械化が出来ないので いまでも昔ながらにしゃがみこんで植え付けます。
(最近知ったのですが、腰を上げたまま植える人もいるそうです)この仕事は太った人は厳しいですね~わさび農家には太った人はいません。
しかし腰痛持ちは多くなります。
写真 父
(最近知ったのですが、腰を上げたまま植える人もいるそうです)この仕事は太った人は厳しいですね~わさび農家には太った人はいません。
しかし腰痛持ちは多くなります。
写真 父

植え付けくわ
これが特注!植え付けくわです。植え付ける時一番気をつけることは、植える苗の毛の周りに細かい砂が行くようにする事です。
そうすることにより、早く苗が作土に定着し、また植えたばかりの苗が倒れにくくなります。といってもなかなか熟練の技が必要です。わさびのできふできは植え付けてからの2~3ヶ月の生育が重要なので、特に神経を使います。
そうすることにより、早く苗が作土に定着し、また植えたばかりの苗が倒れにくくなります。といってもなかなか熟練の技が必要です。わさびのできふできは植え付けてからの2~3ヶ月の生育が重要なので、特に神経を使います。

植え付け作業
1坪あたり70本から80本 (25センチ程度の間隔)で植え付けます。苗には収穫したわさびから株分けして取れた苗(分根苗ぶんこんなえ)と 種から育てた苗 (実生苗 みしょうなえ)、バイオ苗 (わさびの成長点の細胞だけを試験管の中で純粋培養し増やしたもの)があります。
写真の家では平均的大きさのわさび田で、6坪あります。苗にして450本を植え付けます。植える時間は1人で1時間半くらいかかります。
写真の家では平均的大きさのわさび田で、6坪あります。苗にして450本を植え付けます。植える時間は1人で1時間半くらいかかります。
日除け作業
4月下旬頃から10月頃まで有東木では、日除けのための寒冷紗をかけます。
どのわさび田にもかけるわけではありませんが空が開けていて、日差しを遮る木々が無い田では、寒冷紗をかけた方がわさびの生育がいいので、写真のような寒冷紗(遮光率70%)をかけます。(寒冷紗は大きなホームセンターで扱っています)
毎年台風などで、傷んでしまうので修理をしながらの寒冷紗かけで、なかなか大変な仕事です。
どのわさび田にもかけるわけではありませんが空が開けていて、日差しを遮る木々が無い田では、寒冷紗をかけた方がわさびの生育がいいので、写真のような寒冷紗(遮光率70%)をかけます。(寒冷紗は大きなホームセンターで扱っています)
毎年台風などで、傷んでしまうので修理をしながらの寒冷紗かけで、なかなか大変な仕事です。



草取り・ごみとり
常に水が流れているわさび田にも草が生えます。そのまま放っておくとわさびの成長を妨げるので早めにとります。
また枯葉等のごみも水の流れを止めてしまうのでやはりとります。植えてからも日ごろからの見回りを怠らず、わさび田を管理する事がとても大事です。
写真は植えて2ヶ月のわさびの根元に生えた雑草(はこべ)。
また枯葉等のごみも水の流れを止めてしまうのでやはりとります。植えてからも日ごろからの見回りを怠らず、わさび田を管理する事がとても大事です。
写真は植えて2ヶ月のわさびの根元に生えた雑草(はこべ)。

防寒作業
11月後半から3月上旬までの間、寒い環境のわさび田には寒冷紗(かんれいしゃ)と呼ばれる目の粗い布かビニールをかけてやります。
寒い時期の細かい作業なのでとても大変です。写真はビニールをかけてある様子です。
寒い時期の細かい作業なのでとても大変です。写真はビニールをかけてある様子です。

収穫
1年半ほどたつと収穫の時期が来ます。わさびは、適度な水さえあれば、1年中収穫が可能です。
注文や市場の動向を見て収穫していきます。わさび農家をやっていて一番楽しみな時です。
注文や市場の動向を見て収穫していきます。わさび農家をやっていて一番楽しみな時です。

運び出し
1つのコンテナにわさびを1杯入れると15キロほどになります。ほんの30年前までは林道もなく、もちろんモノラックもなくすべて人力でやっていた事を思うと、先祖の人々の大変さがわかります。
今はほとんどモノラックが引いてあり、力仕事というものがなくなりました。
今はほとんどモノラックが引いてあり、力仕事というものがなくなりました。

コンテナの正しい持ち方
コンテナの持ち方にはコツがあります。それは利き腕側の腰骨の上にコンテナのへりをかけて利き腕でコンテナを持ち、コンテナの重さに対してバランスをとるように体を傾ける。 このとき腕は伸ばしたままである。こうする事により案外楽に持つことができます。私はプロなので両側に持つ技を習得しています。

ホンダアクティSDX寒冷地仕様
すべての軽トラの中で選ぶならこれしかない!ハンドリング、4WD性能、経年変化などどれをとっても最高である、仕事柄いろいろな軽トラにのる機会があるが 「こんなに違うんだ」の1台。
注文つけるとするとターボがほしいそれだけである。(有東木は坂がキツイ!)
以前乗っていた前の型のホンダアクティは13万キロ乗ってもエンジン元気ハンドルのがたも少なく、いまでも車の修理工場の代車として元気にやっています。 (^o^)
注文つけるとするとターボがほしいそれだけである。(有東木は坂がキツイ!)
以前乗っていた前の型のホンダアクティは13万キロ乗ってもエンジン元気ハンドルのがたも少なく、いまでも車の修理工場の代車として元気にやっています。 (^o^)

わさび仕分け作業
収穫してきた砂つきのわさびを洗い、1つの株を、根わさび、苗(そのまま、またわさび田に植えます)茎(わさび漬けの原料になる)などに分ける作業。(詳しくはわさび図鑑で)
林道がない時代はすべて収穫したそのわさび田で、この仕分け作業をやっていました。
冬などは寒いので簡易ビニールハウスなどをわさび田に作り作業をやったものです。
子供達が使っていたベビーバスを洗い桶にしていますがとっても重宝しています。
林道がない時代はすべて収穫したそのわさび田で、この仕分け作業をやっていました。
冬などは寒いので簡易ビニールハウスなどをわさび田に作り作業をやったものです。
子供達が使っていたベビーバスを洗い桶にしていますがとっても重宝しています。

毛とり作業
わさび仕分け作業で洗い分けた根わさびの毛を取ります。この作業は各わさび農家で使う道具がまちまちなのですが、家では百円ショップで買ってきた小刀で削ぎ落とします。大変熟練を要する仕事で、最初のうちはよくわさびを傷つけてしまったものでした。

仕上げ作業
毛をとったわさびを1本1本ブラシで水洗いしていきます。
ブラシをかけるとわさびはとてもきれいになるのですが、あまりかけすぎると逆にわさびを傷つけてしまうので注意が必要です。
水仕事なので寒い時期はとてもつめたく大変です。冬の時期はゴム手袋の中に軍手をはめて2重の手袋で作業をしています。
ブラシをかけるとわさびはとてもきれいになるのですが、あまりかけすぎると逆にわさびを傷つけてしまうので注意が必要です。
水仕事なので寒い時期はとてもつめたく大変です。冬の時期はゴム手袋の中に軍手をはめて2重の手袋で作業をしています。

箱詰め作業
毛を取りそしてきれいにブラシで水洗いされたわさびを、ようやく発泡スチロールの箱に詰めます。
そして、忘れずに納品書をいれPM7時頃宅配便のお兄さんに大事なわさびを託します。
そして、忘れずに納品書をいれPM7時頃宅配便のお兄さんに大事なわさびを託します。
最後までご覧いただきありがとうございます。
少しでもわさび仕事がわかって頂ければ幸いです。
少しでもわさび仕事がわかって頂ければ幸いです。
根わさびの保存方法
わさびの水分が飛ばないように、しっかり ラップでくるんで野菜室に入れて保存して下さい。
1ヶ月は保存できますがなるべく早くお召し上がり下さい。
●ひとこと=新鮮なうちは皮をむかずにそのままおろして下さればいいのですが少しづつ黒ずんで 来てしまいますのでその時は黒い部分を削ってお使いくださいただし、皮の部分に辛味が一番ありますのでなるべく薄く削って下さい。
1ヶ月は保存できますがなるべく早くお召し上がり下さい。
●ひとこと=新鮮なうちは皮をむかずにそのままおろして下さればいいのですが少しづつ黒ずんで 来てしまいますのでその時は黒い部分を削ってお使いくださいただし、皮の部分に辛味が一番ありますのでなるべく薄く削って下さい。